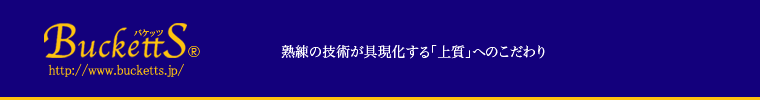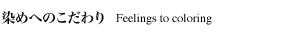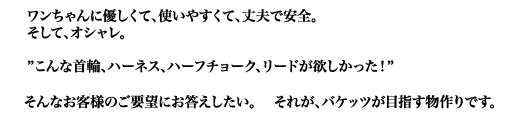
今までの革製犬用品、特に首輪や胴輪などは世界的に見ても革の2枚合わせが主流であり、現在も同様に変化の兆しは見受けられません。
犬に優しく、安全であり、ファッション性がある犬具を製品化するためバケッツはハンドバッグの製作仕様を取り入れ、表革・裏革・クッション・バイリン(補強材)で4層に構造しました。
バケッツが推奨しております5つのコンセプトを網羅した製品とするため、改良、改善を重ねてお客様から使いやすくしかもスタイリッシュとご好評をいただく製品にすることが出来ました。
この仕様に行きつくまでには、サンプル創りの連続であり、完成品に至るまでには技術力の高いバケッツの打ち抜き職人、革漉き職人、縫製職人、金具職人の技が大きな力となりました。


牛皮が海外から輸入されタンナーで水洗い、鞣しなどの工程を経て染色に入りますが、海外で使用される皮革は表面だけの染色(丘染め)を行っているケースが多く見受けられます。
この革を使用して革製品を製作した場合、使用しているうちに表面の染料が剥げて下地が出てくる事があります。
バケッツ製品には芯通し染めされた皮革を使っているので表面の染料が薄くなることはあっても下地に同色系の染色が入っているので丘染めとの違いは歴然としております。
バケッツは良い物をお客様に提供するとこ考えから本染め革(芯通し染め)を使用しております。
| 皮: | 牛皮が海外から輸入され、タンナーで手つかずの状態の時の呼称です。 |
| 革: | タンナーで下処理、鞣し作業終わった皮革の呼称です。 |
| タンナー: | 皮から革に加工する作業=鞣し(なめし)をtanと言うため、皮革製造業の事をタンナーと呼ぶ。 |
| 芯通し染め: | 染色する際に芯(革の内側)まで染色する染め方。 |
打ち抜き職人、革漉職人
皮革打ち抜き職人は、一枚一枚(一頭一頭)の皮革の違いなどを把握し、製品に対して適正な皮革部位の打ち抜きを行える技量が要求されています。
皮革には、焼印もあれば牛同士の喧嘩などによるキズなどがあり、製品作りに適さない皮革部位があります。
長年の経験を元にバケッツの高い品質要求に向く打ち抜き部位を選び、縫製過程前までの作業を行い、無駄を極力省く技量を持つ打ち抜き職人がバケッツの支えとなっております。
ここまでの作業は、厳選した皮革の管理、染色工程での完成度、打ち抜き職人の技が一体となって出来上がるものだと思っております。

これらの工程が終了し、縫製作業に移る前の大切な作業が革漉作業の部門となります。
バケッツ製品はハンドバッグ製作と同様の作業工程を経て製品にしておりますので、革漉作業は全体のシルエットを作るため、スムーズな縫製をするために大変重要な作業となります。
厚く漉く部分、薄く漉く部分など緻密な技量が必要となり、これによって製品の可否が決定されると言っても過言ではありません。

縫製職人
バケッツ製品を縫製している職人は、ハンドバッグ製作縫製職人として45年の職人歴を持っております。
女性用ハンドバッグを製作するためには40〜50位の皮革パーツをパズルの様に繋ぎ合わせる工程を経て製品となります。
バケッツが製作している犬具の皮革パーツは少ないのですが、職人泣かせとも言われる細かい作業が多いため縫製難度が高く、当社の5つのコンセプトを十分に理解した縫製職人がミシンを踏んでおります。
40年以上のキャリアを積んできたバケッツの縫製職人は、いろいろな問題に答えを見つけられる沢山の引き出しを持っており、特に特注品の製作ではその知識と優れた技に支えられてお客様のご要望にお答えできる完成度が高い製品が出来上がっております。
金具職人
よそから持ち込んだ金具を模造する事は容易いことですが、長年の経験と日々の精進で磨き蓄積してきた知識と技術を元にいかに多くの引き出しを持てるかが職人のレベルと考えられます。
バケッツの金具を製品化した職人は、様々な角度からの疑問に答えられる引き出しを持ち、それを具現化する高い技術を持ち合わせた匠です。

◆意匠登録/取得特許
首輪意匠登録取得 登録第1137592号
ハーネス意匠登録取得 登録第1150648号
中華人民共和国意匠登録取得 登録第267903号
ハーフチョークチェーンカラー意匠登録取得 登録第1266109号
首輪特許取得 特許第3832806号